- 1. 【🎞️】【歯科医監修】親知らず抜歯後に食べていいもの・ダメなもの|時期別メニュー付き
- 2. 🍽 抜歯後いつから食事できる?タイミングの目安
- 2.1. ⏰ 抜歯当日の食事は何時から可能?
- 2.2. 💉 麻酔が切れるまでの注意点
- 2.3. 🧊 抜歯直後に避けたい行動(うがい・熱いもの)
- 3. 🥄 時期別|おすすめの食べ物と注意点
- 3.1. 📅 抜歯当日:ゼリー・ポタージュなど
- 3.2. 📅 抜歯翌日〜3日:柔らかく噛まなくて済むメニュー
- 3.3. 📅 4日目以降:徐々に普通食へ移行するコツ
- 3.4. 🍱 1週間後の目安と固いものへの注意点
- 4. ❌ NG食品一覧|傷口を悪化させるリスクがある食べ物
- 4.1. 🌶 香辛料・炭酸・アルコール
- 4.2. 🍘 硬いもの(せんべい・ナッツ)
- 4.3. 🥤 ストロー・吸う動作がNGな理由
- 5. 👨⚕️ 歯科医がすすめる|回復を助ける食事と栄養素
- 5.1. 🥚 たんぱく質・ビタミン類の役割
- 5.2. 🥦 抗炎症・免疫力UPに効果的な食品
- 5.3. 🥤 栄養補助飲料は使ってもいい?
- 6. 🍴 実例紹介|抜歯後におすすめの具体的メニュー
- 6.1. 🥣 コンビニで買えるメニュー例
- 6.2. 🍚 自宅で簡単に作れる時短レシピ
- 6.3. 🍜 食べやすい・飲み込みやすい工夫
- 7. 😖 よくあるトラブルと食事の関係
- 7.1. 🩸 出血が止まらない時の対処
- 7.2. 🦷 ドライソケットと食事の関係
- 7.3. 🤢 食べ物が詰まったときの対処法
- 8. 💬 よくある質問(Q&A)
- 8.1. ❓ 抜歯後すぐにアイスは食べていい?
- 8.2. ❓ 食事で痛みが増す場合どうする?
- 8.3. ❓ 片側だけで噛んでも大丈夫?
- 9. 📝 まとめ|親知らず抜歯後の食事は「無理せず・慎重に」
- 10. 江戸川区篠崎で親知らずの抜歯をご検討中の方へ
- 11. 【動画】横向きに埋没した親知らずを抜かないと?
- 12. 筆者・院長

🦷親知らずの抜歯後、「いつから食べていいの?」「何を食べたらいいの?」と悩む方は多いのではないでしょうか。傷口の回復を早めるには、食事のタイミングや内容選びがとても重要です。この記事では、抜歯直後から1週間後までのおすすめメニューやNG食品、注意点を時期別にわかりやすく解説します。無理なく安全に食事をとるためのポイントを、歯科医の視点からご紹介します。
【🎞️】【歯科医監修】親知らず抜歯後に食べていいもの・ダメなもの|時期別メニュー付き
🍽 抜歯後いつから食事できる?タイミングの目安
⏰ 抜歯当日の食事は何時から可能?
親知らずの抜歯後は、麻酔が完全に切れてから食事を開始するのが基本です。麻酔が効いているうちに食事をすると、唇や舌を噛んでしまう恐れがあるため、目安として抜歯から2〜3時間後をひとつの基準にしましょう。

💉 麻酔が切れるまでの注意点
感覚が戻るまでの間は、水分補給にとどめ、できるだけ刺激物や噛む行為は避けてください。また、誤って傷口を触ってしまうと出血の原因になるため、口の中をいじらないよう注意が必要です。
🧊 抜歯直後に避けたい行動(うがい・熱いもの)
抜歯直後の強いうがいや熱い飲み物は、血餅(けっぺい)※かさぶたのようなものを流してしまう恐れがあります。血餅は治癒に重要な役割を果たすため、術後24時間はやさしくゆすぐ程度にし、飲食物は常温〜ぬるめにすることが望ましいです。
🥄 時期別|おすすめの食べ物と注意点
📅 抜歯当日:ゼリー・ポタージュなど
抜歯直後は患部が出血・腫れやすいため、刺激の少ない冷たい・柔らかい食品を選びましょう。ゼリー、プリン、豆腐、冷ましたポタージュスープなどがおすすめです。ただし、ストローは使用NG。吸う動作が血餅を剥がしてしまうリスクがあります。

📅 抜歯翌日〜3日:柔らかく噛まなくて済むメニュー
この時期はまだ傷口が安定していないため、引き続き噛まずに食べられる食品を選びます。おかゆ、うどん、温めすぎていないスープ、スクランブルエッグ、バナナなどが良いでしょう。熱すぎ・辛すぎのものは炎症を悪化させる恐れがあります。
📅 4日目以降:徐々に普通食へ移行するコツ
痛みや腫れが落ち着いてきたら、よく煮込んだ野菜や柔らかい白身魚、鶏ひき肉など、噛む力が少なくても食べられるメニューへ段階的にシフトしましょう。ただし、抜歯側では噛まないように意識し、反対側でそっと食事するのが安全です。
🍱 1週間後の目安と固いものへの注意点
1週間ほど経過して違和感がなければ、少しずつ通常食に戻して構いません。ただし、せんべい・ナッツ・フランスパンなどの硬いものは避け、繊維質で詰まりやすい食材(もやし・ごぼうなど)にも注意が必要です。食後はうがいや優しい歯磨きで清潔を保ちましょう。
❌ NG食品一覧|傷口を悪化させるリスクがある食べ物
🌶 香辛料・炭酸・アルコール
刺激の強い食べ物や飲み物は、傷口の炎症を悪化させたり、痛みを増やす原因となります。唐辛子などの香辛料、炭酸飲料、アルコール類は抜歯後少なくとも3〜5日は避けましょう。特にアルコールは血行を促進して出血を助長するため厳禁です。

🍘 硬いもの(せんべい・ナッツ)
硬くて噛む力が必要な食材は、縫合部や血餅に負担をかけるリスクがあります。せんべい、ナッツ、フランスパンなどは、最低でも1週間程度は控えるのが安心です。無意識に抜歯部で噛んでしまうと、傷が開いてしまう恐れもあります。
🥤 ストロー・吸う動作がNGな理由
ストローや麺を「すする」行為は、**口腔内の圧力を変化させ、血餅を剥がしてしまう(ドライソケット)**原因になります。抜歯後3日間は特に注意が必要で、飲み物はコップでゆっくり飲むようにしましょう。
👨⚕️ 歯科医がすすめる|回復を助ける食事と栄養素
🥚 たんぱく質・ビタミン類の役割
抜歯後の傷口を早く治すには、たんぱく質とビタミンの摂取が欠かせません。たんぱく質は新しい細胞の再生に必要で、豆腐・卵・白身魚などが適しています。ビタミンCやビタミンAは粘膜の修復や免疫力向上に効果があり、かぼちゃやにんじんなどの柔らかく調理した野菜で取り入れましょう。
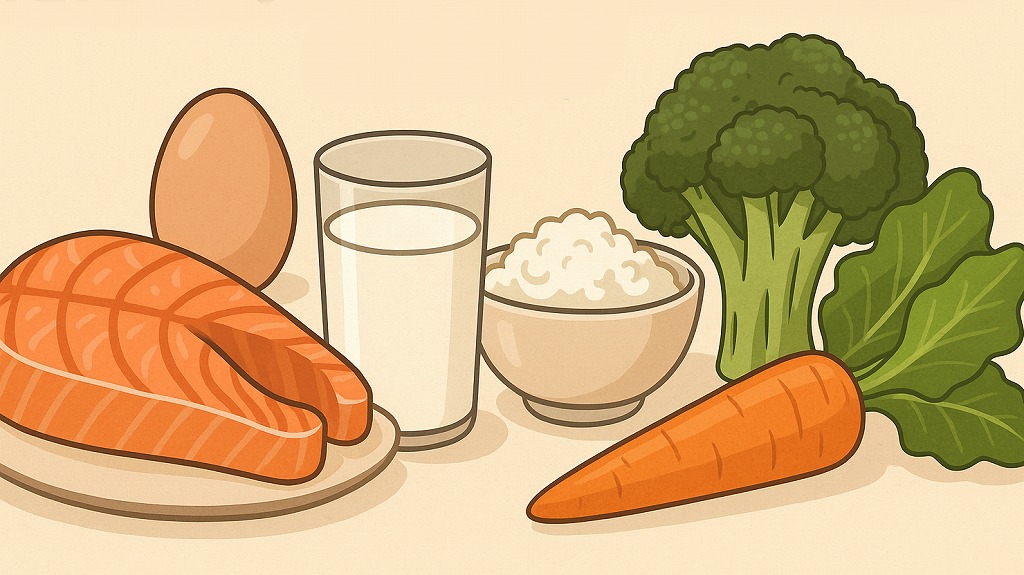
🥦 抗炎症・免疫力UPに効果的な食品
ブロッコリー・小松菜・ほうれん草などの緑黄色野菜には、抗酸化作用を持つビタミンEやカロテノイドが豊富です。また、ヨーグルトや味噌汁などの発酵食品も腸内環境を整え、間接的に免疫力を高めます。いずれも加熱・ペースト化すれば傷口に負担なく摂取可能です。
🥤 栄養補助飲料は使ってもいい?
食欲がない時や食事が十分に摂れない時は、市販の栄養補助飲料を取り入れるのも一案です。ビタミン・ミネラルがバランスよく含まれたものを選びましょう。ただし、冷やして、ストローを使わずに飲むことが大切です。
🍴 実例紹介|抜歯後におすすめの具体的メニュー
🥣 コンビニで買えるメニュー例
抜歯後の食事は、無理に手作りしなくても大丈夫。コンビニで手軽に手に入る以下のような食品が活躍します:
- プリン、ゼリー、茶碗蒸し
- とろろ、温泉卵
- おかゆや雑炊(レトルト)
- ポタージュスープ(冷製も◎)
※買ってすぐ食べられるうえ、温め不要で負担が少ないものを選ぶと安心です。
🍚 自宅で簡単に作れる時短レシピ
「少しでも自炊したい」「栄養も取りたい」という方には、以下のような簡単レシピがおすすめです:
- 卵とじうどん:やわらかめに茹でて、卵をとじるだけ
- かぼちゃポタージュ:レンジで加熱後にミキサーにかけて
- シラス入り雑炊:ご飯と出汁で煮込み、シラスと卵を追加
食材は火を通して柔らかくすることがポイントです。
🍜 食べやすい・飲み込みやすい工夫
痛みや腫れがある時は、飲み込むだけでも苦痛になることがあります。そんなときは:
- 少し冷まして常温に
- とろみをつける
- 小さめスプーンで少量ずつ口に入れる
また、噛まずに飲み込めるかどうかを目安に、献立を組み立てるとスムーズです。
😖 よくあるトラブルと食事の関係
🩸 出血が止まらない時の対処
食事中や直後に少量の出血が見られることはありますが、出血がダラダラと続く場合は注意が必要です。まずは清潔なガーゼを10〜15分しっかり噛んで圧迫止血を行いましょう。それでも止まらない場合は、すぐに歯科医院へ連絡してください。アルコール摂取や熱い食事が出血を悪化させることがあります。
🦷 ドライソケットと食事の関係
抜歯後の穴にできる「血餅(けっぺい)」が失われると、骨が露出して強い痛みを伴う「ドライソケット」を引き起こします。これはストローで吸う、すすり食い、強いうがいなどによって起こるため、術後数日は控えることが重要です。
🤢 食べ物が詰まったときの対処法
抜歯した穴にご飯粒や繊維質な野菜などが詰まることがあります。無理に舌や指で取ろうとすると傷を刺激する恐れがあるため、軽くうがいをするか、数日後に自然に排出されるのを待つのが安全です。どうしても違和感が取れない場合は、歯科での清掃を依頼しましょう。
💬 よくある質問(Q&A)
❓ 抜歯後すぐにアイスは食べていい?
はい、冷たいアイスは一時的に腫れや痛みを和らげる効果があります。ただし、アイスクリームは糖分が多く、傷口に残ると細菌繁殖の原因になるため、食後は水で軽く口をゆすぐようにしましょう。チョコチップやナッツ入りなど「硬いもの混入」は避けてください。
❓ 食事で痛みが増す場合どうする?
痛みが強い場合は無理に食べず、栄養補助飲料やスープなどに切り替えるのが賢明です。痛みが続く場合は、処方された鎮痛剤を使用し、必要であれば歯科医院へ相談しましょう。傷の治り具合によっては、追加の処置が必要な場合もあります。
❓ 片側だけで噛んでも大丈夫?
はい、抜歯していない側で噛むのは基本的な注意点です。ただし、反対側に過度な負担がかからないよう、柔らかい食材を選んで軽く噛むのがコツです。両側を使うのは、傷口が完全に治癒してからにしましょう。
📝 まとめ|親知らず抜歯後の食事は「無理せず・慎重に」

親知らずを抜歯したあとは、食事のタイミング・内容・食べ方すべてに注意が必要です。無理に通常通りの食事をとろうとすると、出血・感染・ドライソケットなどのトラブルを引き起こす可能性もあります。
大切なのは、麻酔が切れてから、冷たくやわらかいものを少しずつ摂ること。時期に応じて段階的に食事内容を戻し、傷口を守りながらしっかり栄養を取ることが、早期回復の近道です。
不安なことがあれば、自己判断せずに歯科医院へ相談しましょう。食事も治療の一環と考え、**「無理せず・慎重に」**を心がけましょう。抜歯の最適な選択肢をご提案しています。江戸川区で親知らずのご相談は、お気軽に当院へご相談ください。
江戸川区篠崎で親知らずの抜歯をご検討中の方へ

抜歯後の食事は、回復に大きく影響する大切なポイントです。当院では、抜歯後のタイミングやおすすめの食事、注意すべき食品についても丁寧にご説明し、患者様が安心して過ごせるようサポートしています。「親知らずの抜歯後食事」で不安のある方は、江戸川区篠崎の当歯科までお気軽にご相談ください。
【動画】横向きに埋没した親知らずを抜かないと?
筆者・院長

深沢 一
Hajime FUKASAWA
- 登山
- ヨガ
メッセージ
日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。
私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。


